結論からお伝えすると、出産内祝いは親に必ずしも渡す必要はありません。
むしろ、親が「いらない」と言っている場合や、家族の間で感謝の気持ちがしっかり伝わっているなら、内祝いを省略するのも自然な選択です。
「親に渡さないのは非常識?」「他の家庭はどうしてるの?」と不安になる方も多いと思います。
この記事では、「出産内祝い 親 いらない」という悩みに対して、渡さない理由や、マナーある対応の仕方、逆に渡すならおすすめのギフトまでしっかり解説しています。
自分たちの家庭にとっての“ちょうどいい答え”を一緒に見つけていきましょう。
ぜひ、最後まで読んでみてくださいね。
出産内祝いを親に渡さないのは非常識?よくある悩みと現実
出産内祝いを親に渡さないのは非常識?よくある悩みと現実について解説していきます。
それでは、ひとつずつ深掘りしていきますね。
①親に出産内祝いを渡すのはマナー?
出産内祝いのマナーとして「親にも渡さなければ非常識」という話を聞いたことがある方、多いと思います。
でも実は、内祝いの本来の意味は“お祝いをいただいたお返し”です。
なので、出産祝いをもらった相手に感謝の気持ちとしてお返しをするのが基本なんですね。
そのため、親が「いらないよ」と言っていたり、そもそもお祝いの金品を受け取っていないなら、形式的に渡さなくてもOKという考え方もあります。
地域や家庭によってもマナーの捉え方が違うので、「一般的にはどうなのか?」よりも「うちではどうなのか?」が大切になりますよ。
自分の家庭に合った形を探してみてくださいね。
②親に渡さない人は実際に多い?
実際のところ、「親に出産内祝いを渡していない」という声はかなり多くあります。
ママ友同士の会話やネットの掲示板を見ても、「うちは渡さなかったよ」「親から『やめてくれ』と言われた」という事例が目立ちます。
親側も「子どもや孫のために渡しているだけだから、お返しなんていらないよ」と考えるケースが多いようです。
つまり、今どきの親世代は“お祝いのお返し”よりも“無事に産まれてくれてありがとう”という気持ちのほうが強い傾向にあるんですね。
統計こそありませんが、筆者の周りでも「渡さなかった派」が多数派でしたよ。
③非常識と思われるリスクは?
「親に内祝いを渡さないのって、非常識かな?」と不安になる方、多いと思います。
でも、ここで大切なのは“誰が非常識だと思うのか”という視点です。
例えば、親戚や知人など第三者から見たら「親にお返ししないなんて失礼じゃない?」と感じるかもしれません。
でも、当の親が納得していたり、そもそもお返しを望んでいないなら、他人の目を気にしすぎる必要はないですよ。
とはいえ、気になる場合は「ちゃんと感謝の気持ちは伝えてるよ」と一言添えておくと、周囲との軋轢も避けやすくなります。
気持ちを形にする方法は、品物だけじゃないですからね。
④親との関係性で判断は変わる?
親に出産内祝いを渡すかどうかは、正直「関係性」がすべてです。
例えば、ふだんからよく連絡を取る仲で、何でも言い合える親子関係なら、「いらないって言ってたし、渡さなくていいか」と自然に判断できるでしょう。
でも、形式やマナーを大切にするご家庭や、義両親との距離がある場合は、あえて渡しておく方がスムーズなこともあります。
親との関係があたたかければ、形式的な「内祝い」はいらないかもしれません。
一方で、微妙な距離感がある場合は「内祝いを渡す=礼儀をわきまえてる」と思ってもらえることも。
このあたりは、自分たち家族にとって最善のバランスを見つけるのが一番ですね。
親に出産内祝いはいらない理由7選
親に出産内祝いはいらない理由7選について解説します。
- ①出産費用を親が負担している
- ②内祝いは「お返し」であって不要
- ③親が「いらない」と言っている
- ④孫の成長が一番の喜び
- ⑤お金のやり取りを嫌う親もいる
- ⑥内祝いの品物が逆に気を使わせる
- ⑦親子間で感謝の形は別にある
それでは、具体的な理由をひとつずつ深掘りしていきますね。
①出産費用を親が負担している
出産前後にかかる費用を親が援助してくれているケース、実はとても多いです。
病院代やベビー用品、里帰りの交通費まで支援してくれているとなると、むしろ「こちらから内祝いを渡す」という感覚に疑問が出てきますよね。
援助してくれた親に対して、さらに品物でお返しをするのは、逆に「気を遣わせてしまう」可能性も。
実際、「出産に関しては全面的に応援してるからお返しなんて考えなくていいよ」と言ってくれる親も多いです。
そういった経緯があるなら、無理に渡さなくても大丈夫ですよ。
その分、感謝の気持ちはしっかりと言葉や行動で伝えるようにしましょう。
②内祝いは「お返し」であって不要
内祝いの基本的な意味は「お祝いをいただいたことへのお返し」です。
でも、親からの支援は“お祝い”というより“家族としてのサポート”という意味合いが強いんですよね。
だから形式的なお返しをするよりも、気持ちで答える方が自然と考える人も増えています。
とくに最近は「内祝い=形式的な儀礼」になりがちで、親世代のほうが「堅苦しくてイヤ」と思っていることも。
それなら無理に渡さなくてもいい、という選択肢もアリなんです。
品物よりも気持ち、ですよ。
③親が「いらない」と言っている
親から「内祝いなんていらないよ」とはっきり言われた場合、それを無視してまで渡すのは、ちょっとズレた対応になってしまうかもしれません。
お祝いを渡す側も「気持ちだから」と言っているように、お返しもまた気持ちであり、相手の意向を尊重するのが大切です。
とくに、親世代は「お返しをもらうことで逆に申し訳ない」と感じる人も多いです。
そんなときは無理に品物で返そうとせず、心を込めた言葉や孫との時間など、別の形で感謝を伝えるようにしましょう。
「いらない」と言われたら、それを信じて、気持ちで返してあげてくださいね。
④孫の成長が一番の喜び
出産祝いをくれた親にとって、一番のご褒美は「孫の笑顔と成長」です。
正直、物で返してもらうことよりも、写真や動画、LINEでの報告のほうがよっぽどうれしいんです。
「これが生きがい!」なんて言うおじいちゃん・おばあちゃんも珍しくないですよね。
そう考えると、物理的な内祝いを贈ることにこだわる必要はないのかもしれません。
孫の存在自体が何よりの「内祝い」になっているというわけです。
⑤お金のやり取りを嫌う親もいる
親世代の中には「身内で金品のやり取りをするのは気持ちが冷める」と考える人もいます。
とくに現金や高額な内祝いになると、逆に「なんか気を遣うわ〜」と感じさせてしまうかも。
たとえ感謝の気持ちであっても、家族だからこそ「形式にこだわらないでほしい」と思っている場合が多いんですね。
お金のやり取りに敏感な親には、あえて“品物を贈らない”という選択が喜ばれるケースもあります。
その代わりに、電話や直接会って「ありがとう」を伝えるのが効果的ですよ。
⑥内祝いの品物が逆に気を使わせる
親に内祝いを贈ったことで、逆に「何かまた送らなきゃ」と気を遣わせてしまう場合もあります。
特に品物が高価だったり、立派な包装だったりすると、「こんなに気を使わせてしまって…」と申し訳なさそうにされることも。
贈った側は感謝の気持ちのつもりでも、受け取る側の性格によっては「気疲れ」に繋がるんですよね。
そんなすれ違いを避けるためにも、無理して贈らない、というのはやさしい配慮になります。
あくまで、相手がどう受け取るかを想像してみるのがポイントです。
⑦親子間で感謝の形は別にある
親子だからこそ、感謝の伝え方も「品物」じゃなくていいんです。
一緒に食事をしたり、写真付きの手紙を渡したり、ちょっとした会話の中に「ありがとう」が込められていれば、それで十分。
形式よりも、“家族らしさ”が伝わる方法のほうが心に残ります。
「うちの家族っぽいやり方でお返ししよう」という気持ちがあれば、それが最高の内祝いになりますよ。
気持ちがこもっていれば、形は自由なんです。
親への出産内祝いを渡さない場合のマナーある対応法
親への出産内祝いを渡さない場合のマナーある対応法を紹介します。
では、ひとつずつ見ていきましょう〜!
①言葉と感謝の気持ちを丁寧に伝える
内祝いを渡さない代わりに一番大事なのが、「感謝の気持ちを言葉でしっかり伝える」ことです。
たとえば電話で、「本当にありがとう。おかげで無事に出産できたよ」とか、「助けてもらってありがたかったよ」など、具体的に伝えると気持ちがグッと伝わります。
言葉ってシンプルだけど、やっぱり一番ストレートに気持ちが伝わりますよね。
特に親世代は、物より気持ちを重視する人が多いですから、「言ってくれて嬉しかったよ」と喜んでもらえる可能性が高いです。
もちろん、直接会って伝えられるならなおさら最高です!
「なんかあげないと…」と悩む前に、まずは言葉を大事にしてみてくださいね。
②お礼の手紙や写真を添える
内祝いの品の代わりとして、「手紙」や「写真」を渡すのもとても効果的です。
お祝いをもらった親へ向けて、「ありがとう」の気持ちを文字にして書いた手紙は、意外とグッとくるものです。
孫の写真を何枚か印刷して、かわいいアルバムにまとめて贈ると、より心のこもった内祝いになります。
LINEやSNSでは見ているかもしれませんが、やっぱり“手に取って見られるもの”って、特別感があるんですよね。
アルバムまでは大変…という方は、写真付きのメッセージカードでも十分です!
「成長記録を見せてもらえるのがうれしい」と思っている親はたくさんいますよ。
③孫との時間をプレゼントする
内祝いを品物で贈る代わりに、「孫との時間」をプレゼントするのも素敵な選択です。
例えば、実家に顔を出して、赤ちゃんの顔を見せてあげたり、一緒にごはんを食べるだけでも、親にとっては最高のプレゼントになります。
遠方でなかなか会えない場合でも、オンラインビデオ通話をしたり、「◯ヶ月記念動画」を作って送ってみるのもアリですよ。
「今度◯◯に一緒に行こうか?」とちょっとしたレジャーに誘ってみるのも喜ばれます。
時間の共有って、お金で買えない分だけ、心に残る贈り物になりますからね。
しかも赤ちゃんが成長していく過程を見られるって、本当に幸せなことなんです。
④出産報告を丁寧にする
内祝いをしない場合は、「出産報告をしっかり丁寧にする」ことも大切です。
たとえば、出産直後ではなくても、「落ち着いたから改めて報告するね」と手紙や電話で状況を丁寧に伝えれば、それだけで感謝は十分伝わります。
「元気に生まれました!〇〇gで、顔はパパ似かな?笑」など、少しユーモアを交えると親しみやすくなりますよ。
病院での様子、退院後のエピソードなどを話すと、親としては「そこまで話してくれるなんて…!」と感激するもの。
とくに親は「うちの子も親になったんだなぁ」としみじみ感じる瞬間でもあります。
報告を丁寧にすることで、あえて品物を贈らなくても“ちゃんとしてる”印象を残せるので安心です。
親に出産内祝いを渡す場合のおすすめギフト5選
親に出産内祝いを渡す場合のおすすめギフト5選を紹介します。
それでは、親に贈って喜ばれやすいギフトをひとつずつご紹介しますね。
①高級なお菓子や和菓子
定番ではありますが、やっぱり「お菓子ギフト」はハズさない内祝いです。
特に、ちょっと高級感のある和菓子や洋菓子を選ぶと、「自分たちでは買わないからこそ嬉しい!」という声が多いです。
たとえば、〈とらや〉の羊羹や、〈資生堂パーラー〉の焼き菓子など、有名店のスイーツは特別感がありますよね。
日持ちするものを選べば、ゆっくり楽しんでもらえるのでおすすめです。
「甘いもの好きな親ならまずコレで間違いない」と思ってOKです!
②上質なタオルや日用品
実用的でありながら高級感もある「今治タオル」などは、親世代にも大人気です。
普段使うものだからこそ、良いものをもらうと嬉しいという声も多数。
「自分で買うにはちょっと贅沢かな」というレベルのものを選ぶと、ちょうどいい内祝いになります。
日用品の中でも、消耗品ではなく長く使えるものを選ぶと、しっかり感も伝わりますよ。
他にも、天然素材の石けんセットやアロマアイテムなども人気があります。
③グルメカタログギフト
「何を贈ればいいか分からない」「好き嫌いが分かれそう」というときに便利なのが、カタログギフトです。
最近のグルメ系カタログは本当にレベルが高くて、有名店の肉や海鮮、スイーツまで選べる内容になっています。
「自分で選べる」ことで、受け取る側も満足度が高いのがポイントです。
特に、義両親など“少し気を使いたい相手”にはカタログギフトがベストチョイスかもしれません。
価格帯も3,000円〜1万円以上まで選べるので、予算に応じて選びやすいのも◎。
④孫の名前入り記念品
親にとっての“最愛の存在”である孫の名前が入ったギフトは、感動度がかなり高いです。
例えば、名前入りのフォトフレームや食器、時計など、「実用性+記念性」があるものがおすすめ。
名入れアイテムは、見えるところに飾ってくれることも多く、「孫がそばにいる気がする」と喜ばれます。
オーダーメイドなので少し時間がかかりますが、その分気持ちも伝わりやすいですよ。
名入りギフトは“特別感”を出したいときにピッタリです!
⑤実用性の高いおしゃれギフト
親が使いやすく、かつちょっとオシャレ感もある実用品も人気です。
例えば、保温性のあるマグカップ、電動歯ブラシ、肩こりグッズなど、健康を気づかうアイテムは喜ばれやすいです。
特に最近は、おしゃれな雑貨ブランドとコラボしたアイテムも増えていて、「あ、これ欲しかったやつだ!」と好評なことも。
実用性がありながら“ちゃんと選んだ感”が伝わるので、内祝いとしても印象が良いんですよ。
「迷ったら日常的に使えるもの+少しだけ贅沢」がベストですね!
親に出産内祝いを渡すべき?判断に迷ったときの考え方
親に出産内祝いを渡すべきか迷ったときの考え方をお伝えします。
「どうしよう…渡すべきかな?」と迷っている方は、この視点を参考にしてみてくださいね。
①家庭のルールを尊重する
出産内祝いの判断って、「家庭ごとの文化」が大きく関わってきます。
たとえば、自分の実家はカジュアルでも、義実家はしっかりマナー重視…という場合もありますよね。
そういうときは、“どちらの家のルールに合わせるか”をまず考えるのがポイント。
もちろん、どちらにも配慮したい気持ちは分かりますが、片方の親の価値観を優先することも時には必要です。
親族間でトラブルにならないよう、事前にリサーチしておくと安心ですね。
②親の性格や価値観を思い出す
親に内祝いを渡すべきかは、「その親がどういう人か?」によっても大きく変わります。
たとえば、几帳面で形式を大事にするタイプの親なら、たとえ「いらないよ」と言っていても、形だけは渡しておいたほうが安心です。
逆に、「気持ちだけで十分」という柔軟な親なら、感謝の言葉だけで済ませても問題ないでしょう。
結局のところ、親の性格を知っているのはあなた自身ですから、「この人ならどう感じるかな?」と一歩引いて想像してみると、答えが見えてきますよ。
無理して形式に縛られすぎないでくださいね。
③パートナーとよく話し合う
意外と忘れがちですが、出産内祝いの判断は「夫婦の連携」がとても大事です。
特に義両親に関することは、パートナーの意見をしっかり聞いておかないと、あとでトラブルになることも。
「うちの親には渡さなくても大丈夫」「いや、うちの親はちゃんとしてないと気にする」など、家庭ごとの価値観があるんですよね。
夫婦で足並みをそろえて、どうするか決めておくと、お互いにストレスが減りますよ。
モヤモヤを放置せず、しっかり話し合ってみてくださいね。
④もらった金額で線引きする
少し現実的な話になりますが、内祝いを渡すかどうかは「金額」で判断してもOKです。
一般的には、「いただいた額の半額〜3分の1程度を目安に返す」とされています。
親からのお祝いが数十万円単位だった場合、無理にその額に見合う内祝いをしようとすると負担が大きすぎますよね。
そういうときは、「金額に応じて、あえて内祝いは控えめにする」「代わりに写真や手紙で気持ちを伝える」など、バランスを考えましょう。
すべての贈り物に内祝いを返さなきゃ!と思わなくて大丈夫です。
無理なく、心のこもった方法で感謝を伝えれば、それで十分ですからね。
出産内祝いで親にモヤモヤしないために大切なこと
出産内祝いで親にモヤモヤしないために大切なことをお伝えします。
心がモヤモヤしてしまうのって、やっぱり“正解を求めすぎている”からかもしれません。
そんなときは、ちょっと視点を変えてみてくださいね。
①完璧な正解はないと知る
まず大前提として、「出産内祝いに関する完璧な正解なんて存在しません」。
家族の関係性、親の性格、地域の習慣、そのすべてが違う中で、誰にでも当てはまる「正しい答え」を求めるのは難しいんです。
ネットで「非常識」「当たり前」などいろんな意見が出てきても、それはその人の立場や体験に基づいたもの。
あなた自身の家庭にとって何がベストか?を考えることが一番大切なんです。
周囲の声に振り回されず、自分の中の“納得感”を大切にしてくださいね。
②「感謝の伝え方」にフォーカスする
出産内祝いの本質は「感謝の気持ちを伝えること」です。
それが品物であれ、言葉であれ、行動であれ、気持ちがこもっていれば十分なんです。
形式に縛られすぎて「何を贈ればいいの?」「これで大丈夫かな…」と不安になるよりも、まずは「どうやって感謝を伝えたいか」を考えてみてください。
相手が喜ぶこと、安心すること、笑顔になることを意識してみると、自然と答えが見えてきますよ。
感謝の伝え方はひとつじゃない、ということを忘れずにいましょう。
③マナーよりも家族の絆を大切に
世間の「マナー」にとらわれすぎると、本来の目的である“親子の絆”が見えなくなってしまいます。
「常識だから」と無理に形式を守って、逆に親との関係がギクシャクするなら本末転倒ですよね。
大切なのは、あなたと親との間にある温かい関係です。
その絆を大切にしながら、「我が家に合った形」で内祝いを考えるのがベストなんです。
マナーよりも、愛情と信頼が伝わることの方が、ずっと価値がありますよ。
④気になるなら軽いギフトでもOK
それでも「やっぱり何か渡した方がいいかな…」と少しでも気になるなら、**軽めのギフト**を用意しておくのもアリです。
たとえば、かわいいお菓子セットや、フォトカード付きの簡単な贈り物など、気負わずに渡せるものを選ぶと気持ちがラクになります。
「気を使わせたくない」「でも自分の中でケジメはつけたい」という方にちょうどいい選択です。
この“気になる気持ち”を否定せず、うまく付き合う方法を見つけてあげると、モヤモヤがスッと晴れたりしますよ。
無理に我慢する必要はないし、ちょっとした工夫で心は軽くなるものです。
まとめ|出産内祝いを親に渡さないのは非常識?
出産内祝いを親に渡さないことは、決して非常識ではありません。
大切なのは「親がどう思っているか」と「自分たち家族が納得できるか」です。
親がいらないと言っている場合や、出産費用を支援してくれたケースでは、内祝いを渡さない方が自然な場合もあります。
また、言葉や行動でしっかりと感謝を伝えられれば、それで十分という考え方もあります。
迷ったときは、親の性格や価値観を思い出し、パートナーとしっかり話し合って、自分たちにとって無理のない方法を選んでくださいね。
家族の絆を大切にしながら、モヤモヤのない選択ができるよう、この記事が少しでもお役に立てれば嬉しいです。
参考資料:出産内祝いのマナーまとめ(一般社団法人マナーズ協会)
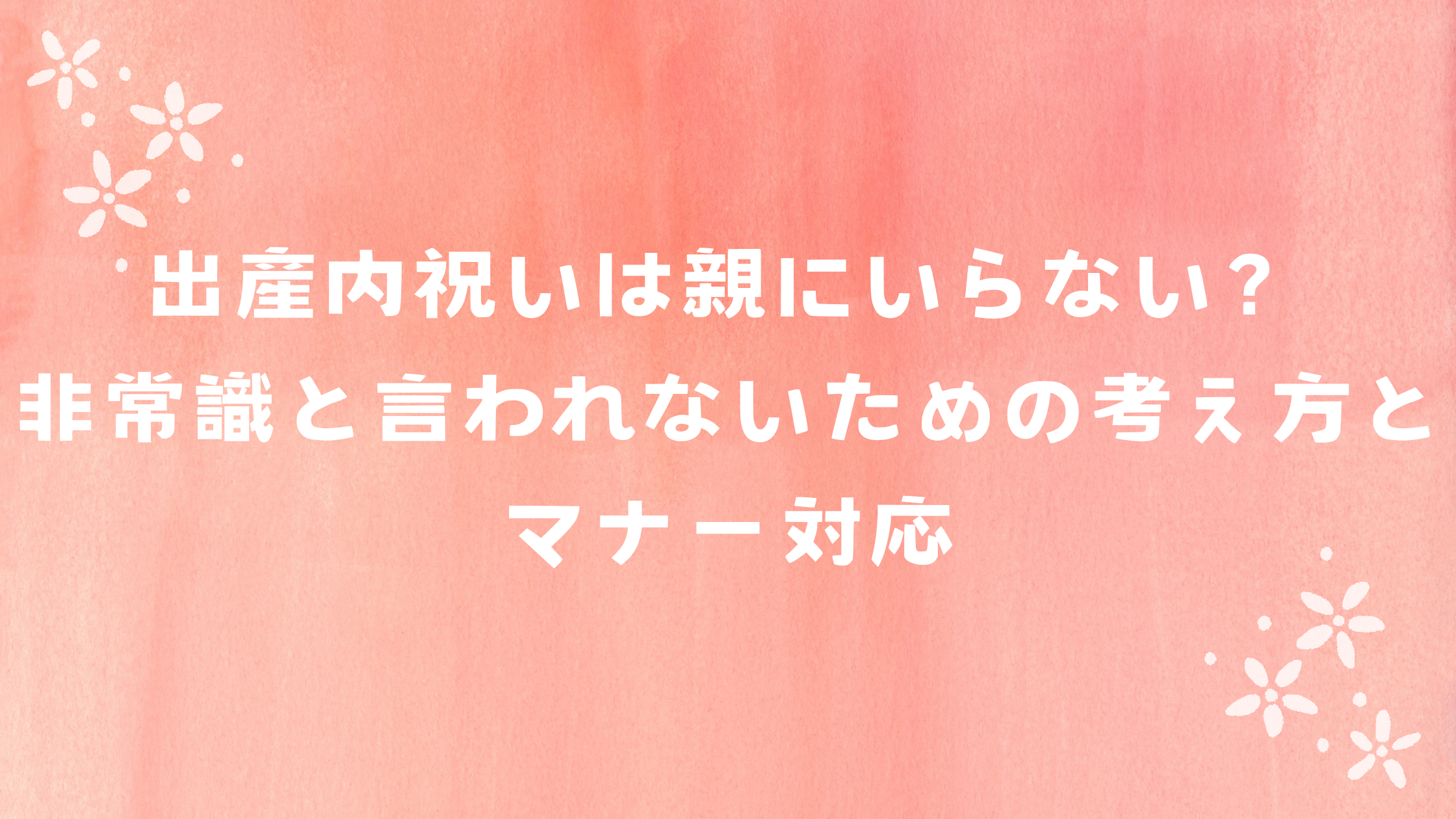
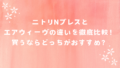
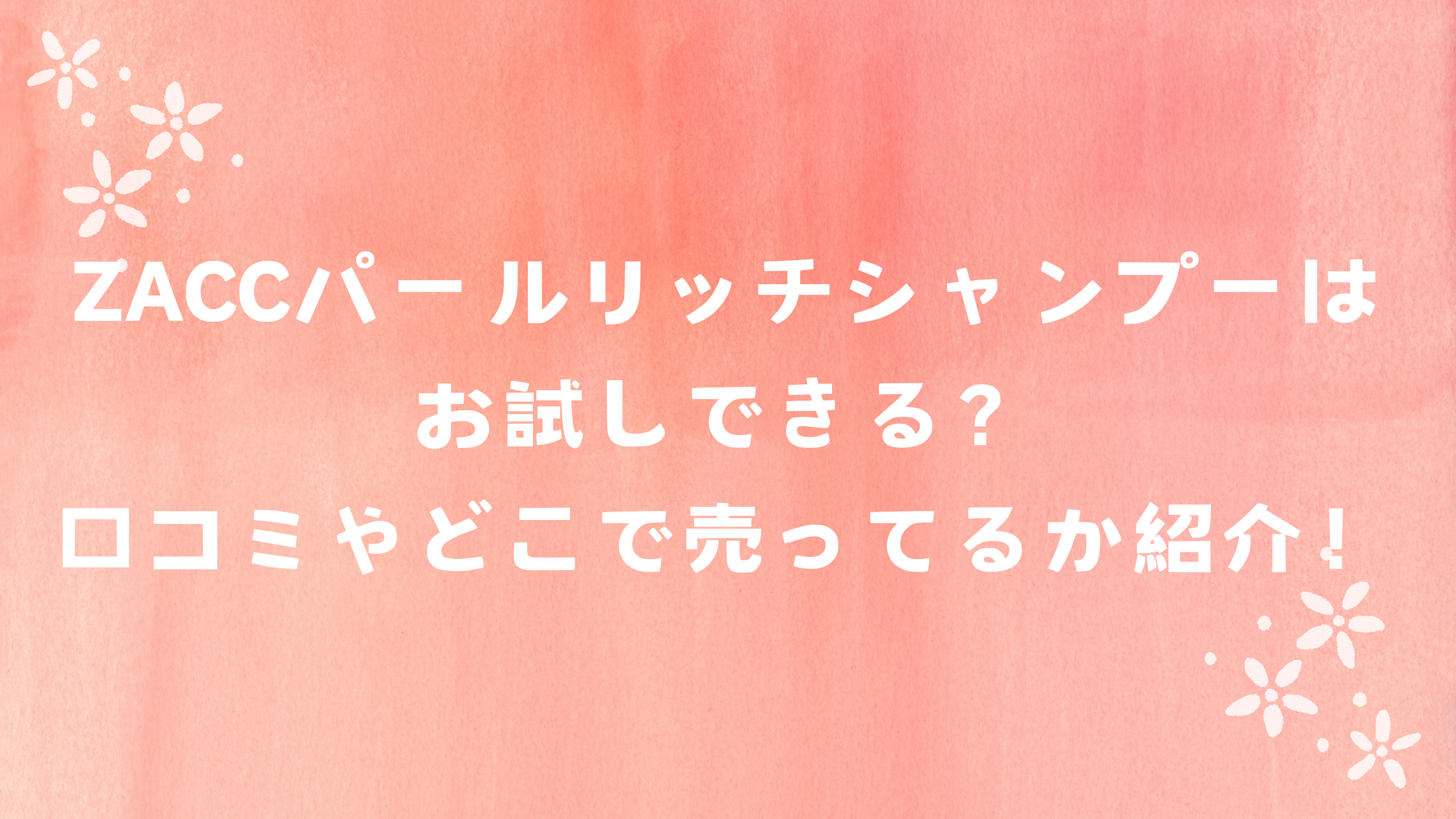
コメント